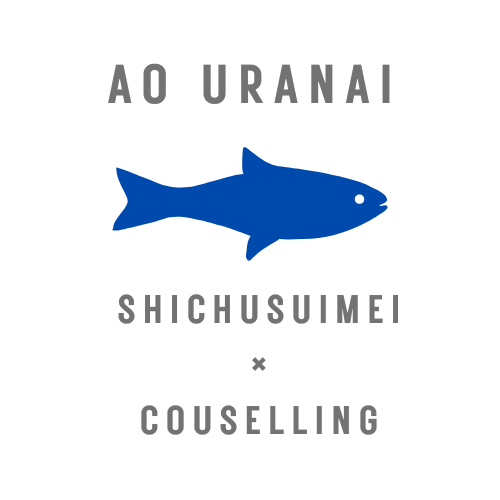悠久の時を超えて受け継がれる叡智 〜四柱推命の歴史を紐解く〜

悠久の時を超えて受け継がれる叡智 〜四柱推命の歴史を紐解く〜
当サイトへお越しいただき、誠にありがとうございます。
ここでは、皆様がご自身の運命を深く知るための道標となる「四柱推命」が、いかにして生まれ、発展を遂げてきたのか、その悠久の歴史についてご紹介いたします。
四柱推命は、単なる「占い」という言葉だけでは語り尽くせぬ、深遠な哲学と緻密な理論に裏打ちされた「運命学の帝王」とも称される学問です。その源流を辿ることは、ご自身の命式(運命の設計図)を、より深く理解する一助となることでしょう。
源流:古代中国の自然哲学
四柱推命の根幹をなす思想は、今から二千年以上前の中国、戦国時代にまで遡ります。それは、万物はすべて「陰」と「陽」の二つのエネルギーから成り立ち、さらに「木・火・土・金・水」という五つの要素(五行)が互いに影響を与え合いながら循環している、という「陰陽五行思想」です。
古代の人々は、天地自然の厳粛な法則の中に、人間一人ひとりの運命もまた組み込まれていると考えました。この壮大な自然哲学こそが、四柱推命が誕生する土壌となったのです。
唐の時代:三柱による運命鑑定の萌芽
時は進み、唐の時代(7世紀〜10世紀)。ひとりの役人であり、優れた運命学者であった**李虚中(りきょちゅう)**という人物が、人の運命を読み解く画期的な手法を確立しました。
それは、人が生まれた「年」「月」「日」の三つの柱、すなわち「三柱」の干支(かんし)を立て、その組み合わせから個人の貴賤や吉凶を判断するというものでした。これが、現代に伝わる四柱推命の直接的な原型であると言われています。
宋の時代:四柱推命の完成
唐代に生まれた運命学は、宋の時代(10世紀〜13世紀)に、徐子平(じょしへい)という人物によって革命的な発展を遂げます。
徐子平は、従来の三柱に、人が生まれた「時刻」を示す「時柱(じちゅう)」を加え、「四柱」としました。これにより、一日に生まれる多くの人を、より詳細に区別して鑑定することが可能になったのです。
さらに彼の最大の功績は、鑑定の中心を、生まれた「日」の干(日干)に置き、これを自分自身(我)としたことです。そして、他の七つの干支との関係性(通変星など)から、その人の持つ性質、才能、そして生涯の運気の流れを読み解くという、現代の鑑定法の基本構造を確立しました。
この偉大な功績から、四柱推命は「子平(しへい)」あるいは「子平学」という別名でも呼ばれるようになったのです。
明・清の時代:理論の深化と体系化
宋の時代に完成された四柱推命は、明・清の時代(14世紀〜20世紀初頭)に入ると、さらなる深化を遂げます。
『淵海子平(えんかいしへい)』や『三命通会(さんめいつうかい)』といった、今日我々が学ぶ上で欠かすことのできない重要な書物が次々と編纂されました。これらの書物によって、格局(命式のパターン)、喜忌(命式にとって良い五行・悪い五行)の判断法、大運(10年ごとの運気)の読み解き方など、複雑な理論が整理・体系化され、四柱推命はより緻密で奥深い学問へと昇華していったのです。
日本への伝来と独自の発展
日本に四柱推命が本格的に伝わったのは、江戸時代中期のことです。中国の文献が舶来し、一部の学者や知識人の間で研究が始まりました。
そして明治時代以降、阿部泰山(あべたいざん)をはじめとする偉大な先達たちの情熱的な研究と実践によって、日本独自の解釈や流派が生まれ、民間に広く普及するに至りました。現代日本の四柱推命は、こうした先人たちが築き上げた礎の上に成り立っているのです。
しかし、現在では一口に四柱推命学といっても様々な流派に別れていて本流から離れてしまっているものも多いようです。
私の身につけた四柱推命学は正統派と言われる泰山流四柱推命学に基づいて現代に合わせて独自の視点、観点に基づいて解き明かすもので、高い的中率を出します。
このように、四柱推命は何千年もの時を超え、数多の賢人たちの手によって磨き上げられてきた、人類の叡智の結晶です。
ご自身の命式を知り、その歴史的背景に想いを馳せる時、鑑定は単なる吉凶判断を超え、人生を豊かに生きるための羅針盤となります。
皆様の人生という名の航路を照らすお手伝いができますことを、心より願っております。
※上記の歴史の流れに関しては諸説ありますので、ご理解の程お願い申し上げます。